令和7年度 帯状疱疹予防接種
帯状疱疹の予防接種について
令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づくB類定期接種に加わりました。この予防接種は、主に個人の疾病予防のために行うもので、接種を受ける義務はありません。対象者の方は、下記のリーフレットもご覧いただき、ワクチンの効果や副反応について十分理解したうえで接種をお受けください。
【帯状疱疹とは】水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治まった後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
対象者
1 接種日において、岡谷市内に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
令和7年度中に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる方(令和7年度は100歳以上の方は、全員対象となります)
- 65歳:昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれ
- 70歳:昭和30年4月2日から昭和31年4月1日生まれ
- 75歳:昭和25年4月2日から昭和26年4月1日生まれ
- 80歳:昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれ
- 85歳:昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれ
- 90歳:昭和10年4月2日から昭和11年4月1日生まれ
- 95歳:昭和5年4月2日から昭和6年4月1日生まれ
- 100歳以上:大正14年4月2日より以前の方
対象となる方には、予診票を同封して個別通知します。
2 接種時に60歳から65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方。
該当する方で接種を希望する方は、健康推進課までお問い合わせください。
※65歳から100歳までの5歳刻みの方につきましては、令和11年度までの経過措置であり、令和12年度以降は65歳の方のみ対象となります。
【対象から除かれる方】
・これまにで生ワクチンを接種したことがあり、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められる方。
・これまでに組換えワクチンを2回接種したことがあり、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められる方。
ワクチンの種類及び接種回数
帯状疱疹ワクチンは、生ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン「ビケン」)と組換えワクチン(シングリックス)の2種類があり、生ワクチンは1回、組換えワクチンは2回接種となります。接種回数や接種方法、接種効果などに違いがあります。詳しくは下記の厚労省作成の説明書をご覧ください。
| 生ワクチン | 組換えワクチン | |
| 接種回数 |
1回(皮膚に接種) |
2回(筋肉内に接種) 通常、2カ月以上の間隔を置いて2回接種 |
| 接種できない方 |
病気や治療によって免疫が低下している方 |
免疫の状態に関わらず接種可能 |
| 接種に注意が必要な方 |
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3カ月以上、大量ガンマグロブリン治療を受けた方は治療後6カ月以上置いて接種してください。 |
血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
定期接種は生ワクチンか組換えワクチンのいずれか一方のみが対象です。両方を接種することはできません。
接種費用
接種費用について、下記のとおり公費負担します。差額は自己負担となります。
| ワクチンの種類 | 生ワクチン | 組換えワクチン |
| 市助成額 |
3,000円/1回 (1回につき3,000円を差し引いた額は自己負担) |
6,000円/1回(2回接種で12,000円) (1回につき6,000円を差し引いた額は自己負担) |
| 非課税世帯の方への助成額 |
4,000円/1回 (1回につき4,000円を差し引いた額は自己負担) |
11,000円/1回(2回接種で22,000円) (1回につき11,000円を差し引いた額は自己負担) |
| 生活保護世帯の方 | 無料 | 無料 |
※市民税非課税世帯に属する方は補助券を発行します。接種する前に、どちらのワクチン(生ワクチンまたは組換えワクチン)を接種するか決めたうえで健康推進課まで申請にお越しください。本人及び同一世帯以外の方が申請にお越しいただく場合は、委任状が必要になりますので、健康推進課へお問い合わせください。生活保護世帯に属する方へは無料券を送付します。
接種方法
対象となる方へは、予診票など個別に通知します。(6月下旬予定)
早めの接種を希望する場合は、ご連絡ください。
組換えワクチンは2カ月以上の間隔を開けて2回接種が必要です。公費で接種するためには年度内に接種を完了する必要がありますので、ご注意ください。(令和7年度接種対象者の方の接種期間は令和8年3月末までです。令和8年4月1日以降の接種は任意接種となり全額自己負担となります。)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種による健康被害は極めて稀ではあるもののなくすことはできないことから、国による救済制度が設けられています。定期の予防接種により健康被害が生じた場合にその健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済制度が受けられます。申請に必要な手続きは、住民票のある市町村が窓口となりますのでご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1177)





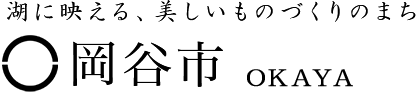
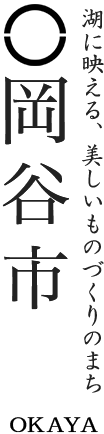





更新日:2025年03月26日