令和7年度市県民税の税制改正について
市県民税の主な改正点(令和8年度以降適用分)
令和8年度の市県民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.給与所得控除の見直し
2.大学生年代の子等に関する特別控除の創設
3.扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
1. 給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。これにより、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
※給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
例えば💡
【配偶者や親族の「扶養控除の適用」に係る「年収」について】
配偶者や親族の令和7年中の収入が、パート・アルバイトなど給与収入のみの場合、給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、市県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
また、給与収入が106.5万円以下(改正前:96.5万円以下)であれば、配偶者・親族自身に市県民税、森林環境税は課税されません。
| 令和7年中の給与収入の金額 (令和7年中の所得金額) |
配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか(注1) | 配偶者・親族自身に「市県民税、森林環境税」が課税されるかどうか(注2) |
| 106.5万円以下 (41.5万円以下) |
対象となります | 課税されません |
| 106.5万円超123万円以下 (41.5万円超58万円以下) |
対象となります | 課税されます |
| 123万円超 (58万円超) |
対象となりません | 課税されます |
注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
注2)市県民税、森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が41.5万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
【改正前と改正後の給与所得控除】
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+80,000円 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+80,000円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
2.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(改正後の要件)の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。
【控除金額】
| 親族等の所得金額 | 控除金額 |
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
3.扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
同一生計配偶者及び扶養親族の前年中の所得要件の見直し
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が、58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。
また、同一生計配偶者の前年の所得要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。
ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得要件の見直し
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。
雑損控除の対象となる資産の所有者の所得要件の見直し
災害により損害を受けた資産の所有者が生計を一にする配偶者その他の親族だった場合について、その配偶者・親族自身の前年中の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。
勤労学生の前年中の所得要件の見直し
勤労学生の前年の合計所得金額の要件が85万円以下(改正前:75万円以下)に引き上げられます。
4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
1.年齢が40歳未満で配偶者を有する者
2.年齢が40歳以上で年齢が40歳未満の配偶者を有する者
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121,1122,1125~1127)





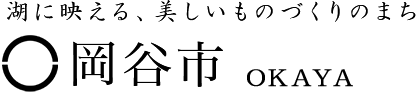
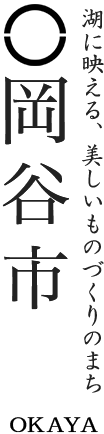





更新日:2025年10月03日