定額減税補足給付金(調整給付金)について(受付は終了いたしました)
本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了いたしました。
制度概要
令和6年分の所得税および令和6年度(令和5年分)の個人住民税において、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税を実施しております。その中で、定額減税しきれない方に対し、支給するものです。
支給対象者
本市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額※1が令和6年分推計所得税額※2又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円)を超える場合は対象外となります。
※1 定額減税可能額とは
・所得税分3万円×(本人+扶養親族数)
・個人住民税分1万円×(本人+扶養親族数)
※2 令和6年分推計所得税額とは
令和6年分所得税額は確定していないため、令和5年分所得税額をもとに推計するもの
支給される金額(調整給付額)
定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げて算定した額
調整給付額算出方法
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額= 所得税分控除不足額
(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
調整給付額=(1)+(2)の合算額を1万円単位で切上げた額
申請方法および支給時期
定額減税補足給付金(調整給付金)の支給対象となる方には、支給のご案内を送付いたしました。
1 公金受取口座※のご登録をされている方(原則、手続不要)
支給決定通知書でご案内した口座に、9月11日(水曜日)にお振込みいたしました。
※公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録されている口座です。
2 公金受取口座のご登録をされていない方(手続必要)
支給対象の方に対して、「支給確認書」を送付いたしました。
お手元に「支給確認書」が届きましたら必要事項を記入して、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)までに、提出の際に必要な書類と併せて同封の返信用封筒で岡谷市に提出するかオンライン申請を行ってください。
●提出書類(提出にあたっては同封の返信用封筒をご利用ください。)
1.「支給確認書」
2.「本人(代理人)確認書類の写し(コピー)」
3.「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」※(受給を辞退する場合は不要)
※今回のお手続きは定額減税補足給付金(調整給付金)を受け取る口座を指定するものであり、公金受取口座を登録するものではありません。
○各数値について重大な相違がある場合
→「相違のあることが分かる関係書類」の提出が必要となります。
相違のある部分に二重線を付して手書きで訂正するとともに、「相違のあることが分かる関係書類」(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書等)の写し(コピー)を追加して提出してください。
●支給の目安
審査のうえ、順次、給付金をご指定の口座へお振込いたします。
市が確認書を受理した日からおおよそ3週間後が支給の目安となります。
(注)申請内容に不備等があった場合は、振込が遅れる場合があります。
(注)申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
○代理申請及び支給対象者以外の口座名義人へのお振込みについて
代理申請及び支給対象者以外への口座名義人へのお振込は可能ですが、代理人が支給確認書等の提出をする場合は、【代理確認・受給を行う場合】の委任欄に支給対象者本人が署名するとともに、委任状のほか、支給対象者本人及び代理人の本人確認書類の提出が必要となります。
代理人は法定代理人、親族、その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方に限ります。
なお、身体上の理由などによる代筆は、代理申請には該当しませんので記入不要です。
◇「委任状」(リンク)(PDFファイル:384.5KB)
◇「委任状」(リンク)(Wordファイル:14.9KB)
○支給確認書の送付先の変更等について
下記に該当する方は、岡谷市で現住所を把握しておらず、送付した支給確認書が届かない可能性があります。
- 令和6年1月1日時点では岡谷市内に住所があったが、1月2日以降に市外に転出をして、郵便局の転居・転送サービスを利用していない方や今年2回以上転居している方
- 入院中、長期出張中等の理由で住民登録されている住所にいない方
上記に該当する方などで、支給対象と思われる方でも、支給確認書が届かない方や、成年後見人等の代理人宛てに送付が必要な方は、「定額減税補足給付金(調整給付金)申請書(様式第2号)」をダウンロードして印刷し、必要事項を入力の上、本人確認書等必要書類を添えて、令和6年9月30日(月曜日)(当日消印有効)までにご提出ください。
※この申請書は、住所地とは別の場所への支給確認書の送付を希望する方などが使用するものです。「支給確認書」が届いた場合は、この申請書は使用せず、支給確認書に記入・返送してください。
この申請を提出いただいた場合、岡谷市において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた現住所に支給確認書を送付します。給付金の受給には、支給確認書の提出が必要です。
◇「定額減税補足給付金(調整給付金)申請書(様式第2号)」(PDFファイル:562.5KB)
提出書類の提出先
岡谷市幸町8番1号
岡谷市役所 庁舎5階 企画政策部企画課
※支所、出張所では受け付けておりませんのでご注意ください。
定額減税補足給付金(調整給付金)の支給に関するお問い合わせ先
岡谷市定額減税補足給付金コールセンター
0120-501-895
受付時間 8:30~18:00(土日祝日も対応いたします。)
(11月30日(土曜日)に、コールセンターの受付は終了しました。)
※定額減税補足給付金(調整給付金)については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、コールセンターでは、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせの前に以下のQ&Aをご覧ください。
定額減税補足給付金(調整給付金)に関するQ&A
Q 私は定額減税補足給付金(調整給付金)の対象者ですか。いくらもらえますか?
A 支給対象者の方には支給対象者の方には令和6年8月21日頃に岡谷市から支給のご案内の発送をいたしました。支給額については、送付した通知をご覧ください。
Q 定額減税補足給付金(調整給付金)の支給対象者や支給額はどのようにして決定しているのですか?
A 個人住民税や推計所得税額などの税情報を基にして、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を利用し、支給対象者・給付額の基本台帳を自動計算で作成します。
Q 定額減税補足給付金(調整給付金)を受け取るには何か手続きが必要ですか。
A 給付金の受取りには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請する必要があります。
対象の方には、手続き方法を記載した支給のご案内を送付いたしましたので、郵送またはオンラインで申請してください。
なお、マイナンバーカードを利用した公金受取口座を登録されている方は、「支給のお知らせ」に記載の口座へ振り込みますので、手続きは不要です。
Q 令和6年1月2日以降に岡谷市へ転入してきたのですが、定額減税補足給付金(調整給付金)はどこの自治体から支給されますか。
A 定額減税補足給付金(調整給付金)を実施するのは、令和6年度に個人住民税を課税した自治体です。必ずしも住民票上の自治体とは限りません。
Q 令和6年1月2日以降に子どもが生まれましたが、定額減税補足給付金の支給対象となりますか。
A 扶養親族数の判定は令和5年12月31日時点となりますので、令和6年中に扶養親族等が出生・逝去した場合ともに、支給額の算定には影響しません。
Q 口座振込ではなく、窓口で給付金を受け取りたい。
A 原則として口座振込の支給のみとしております。(金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合に限り、窓口での現金支給を行います。)
Q 自分が課税か非課税かを教えてほしい。課税状況や扶養状況など確認したい。
A 個人市・県民税の徴収方法が給与からの特別徴収(給与天引き)の場合は、5月下旬以降に勤務先から渡される個人市・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書をご覧ください。それ以外の場合は、6月中旬に個人市・県民税の納税通知書が岡谷市税務課から発送されていますのでそちらでご確認ください。
また、マイナンバーカードを利用して世帯の所得や情報が確認できます。
詳細はデジタル庁HPの「私の情報について(外部サイト)」をご覧ください。
Q 支給確認書を紛失してしまったので、再発行してほしい。
A 岡谷市企画政策部企画課までご連絡ください。
Q 本人確認書類には何が該当しますか?
A 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しのご提出をお願いします。
そのほか、内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 よくある質問もご参照ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html
その他
所得税における調整給付額の算定において、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に、同一生計配偶者やこどもの誕生により扶養親族が増えた場合や失業等により令和6年所得が減った場合に、調整給付額に不足が生じる場合があります。その場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 政策推進担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1521)





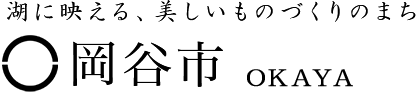
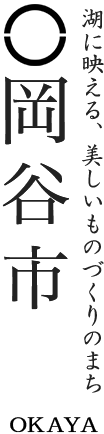





更新日:2024年11月01日