ごみ・資源物の出し方
収集する品目
岡谷市で収集するごみや資源物の品目は以下の通りです。
- 燃やすごみ
- 埋立ごみ
- 草・落ち葉・せん定枝
- 資源物
- プラスチック資源
- 生ごみ
- アルミ缶、スチール缶、金属類
- 使用済乾電池
- 古着・古布
- 古紙(段ボール箱、新聞・チラシ、雑誌、牛乳パック、その他の雑紙)
- 蛍光管・電球
- ガラスびん(透明びん、茶色びん、その他びん)、生きびん(ビールびん、一升びんなど)
- ペットボトル(ラベルとキャップは、プラスチック資源)
「ごみ」の出し方
| 種類 | 袋等 | 袋の大きさ | 出し方 |
| 燃やすごみ | 燃やすごみ指定袋 | 45L・22L・ 10L |
燃やすごみ指定袋に入れて出す。 |
| 埋立ごみ | 埋立ごみ指定袋・ 燃えないごみ指定袋 (文字がオレンジ色) |
45L・22L・ 10L |
埋立ごみ指定袋か、オレンジ色の文字の燃えないごみ指定袋に入れて出す。 |
| 草・ 落ち葉・ せん定枝 |
※透明袋 | 45L以下 | 草・落ち葉は乾燥させ、透明袋に入れて出す。 せん定枝は1本が長さ60cm以下・太さ10cm以下のものを、直径30cm以下に束ねて出す。 |
<注意点>
- 透明袋は、プラスチック資源指定袋などの45L以下の中身が見える透明な袋を指します。レジ袋等の中身が見えない半透明の袋はお使いいただけません。
- 指定袋の代金には、ごみ処理手数料が含まれています。
- ごみは一回の収集で2袋までしか出すことができません。(草・落ち葉・せん定枝も1袋と数えます)
- 資源物は燃やすごみにするのではなく、分別をお願いします。下記「「資源物」の出し方」をご確認ください。
「資源物」の出し方
| 種類 | 袋等 | 袋の大きさ | 出し方 |
| プラスチック資源 | プラスチック資源 指定袋 |
45L・22L | 指定袋に入れて出す。 |
| 生ごみ | 生ごみ指定袋 | 10L | 指定袋に入れて出す。 水を切り、ネット等は入れない。 |
| アルミ缶 | ※透明袋 | 45L以下 | 透明袋に入れて出す。 |
| スチール缶 | ※透明袋 | 45L以下 | 透明袋に入れて出す。 |
| 金属類 | ※透明袋 | 45L以下 | 透明袋に入れて出す。 さびた金属も回収が可能。 |
| 使用済乾電池 | ※透明袋・ 乾電池回収袋(黄色) |
45L以下 | 透明袋に入れて出す。 接点に絶縁テープを貼る。 収集するのは9月・3月の埋立ごみの収集日です。 |
| 古着・古布 | ※透明袋・ ひもで縛る |
45L以下 | 透明袋に入れるか、ひもで縛って出す。 |
| 古紙 | 紙袋か段ボール・ ひもで縛る |
ー | 新聞・広告、雑誌、段ボール、紙パックは種類ごとに分け、ひもで縛って出す。 雑紙は紙袋か段ボールに入れて出す。 |
| 蛍光管・電球 | 購入時の箱・ 紙で包む |
ー | 箱に入れるか、新聞紙等の紙で包んでから、回収コンテナに入れる。 |
| ガラスびん | ー | ー | 透明・茶色・その他の色に分け、回収コンテナに入れる。 生きびんはコンテナに入れずに横に置く。 |
| ペットボトル | ー | ー | キャップとラベルを取り、中を軽く洗ってからボトルをできるだけつぶして、店頭回収ボックスに入れる。 |
<注意点>
- 透明袋は、プラスチック資源指定袋などの45L以下の中身が見える透明な袋を指します。レジ袋等の中身が見えない半透明の袋はお使いいただけません。
- 資源物を出すときは、1回の収集で2袋以上出すことができます。
ごみの出し方に関する注意事項
- 収集場所は、地域の皆様が共同で使用していただく場所です。お互いが気持ちよく使用できるようご協力をお願いします。(収集場所に関するお問い合わせは、各地区衛生自治会へお願いします。)
- 収集場所によって、出せるごみや資源物の曜日や種類が異なります。「家庭ごみ・資源物収集場所マップ」や収集場所に設置してある看板でご確認ください。
- 袋には、必ず氏名(フルネーム)を記入しましょう。
- 袋の口は、中身がはみ出さないように必ず十文字に結びましょう。
- ごみや資源物は早朝から午前8時30分までに出しましょう。収集日の前日に出さないようにしましょう。
- 収集場所に出す際は、ごみや資源物の種類ごとに置きましょう。また、交通の妨げにならないように置きましょう。
- ごみや資源物を出した後は、収集場所に備え付けのネットを丁寧にかけ、カラスなどの被害を防ぎましょう。
ごみ分別ガイド
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 資源化担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1447・1448)





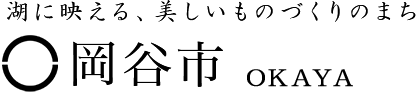
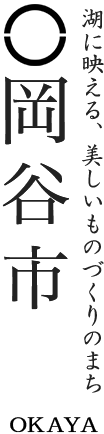





更新日:2023年01月18日