「おかやですすめる食育」情報(2024.11)
食育講演会を行いました

講演会の様子1
11月11日、市役所9階 大会議室において食育講演会を実施しました。今年度は長野県のソウルフードと呼ばれているけれど、諏訪地方ではあまり根づいていない「おやき」をテーマとした講演会でした。
当日は70名の方に参加していただきました。諏訪地方の郷土食とまではなっていない「おやき」ですが、実は「おやき好き」な方が多いということが今回講演会を通してわかりました。
実はおやきが嫌いだった?

講師の小出陽子さん
左の写真の方は、今回の講演会の講師を引き受けてくださった小出陽子さんです。小出さんは、長野市でおやき屋を経営しながら、信州おやき協議会の会長を務めていらっしゃいます。また、銀座にあるアンテナショップにて「粉もん講座」の講師をしたり、テレビのコメンテーターをしています。
小出さんがおやき屋をやり始めたのは40代半ば。当時おやき屋をやっていたお母様がお店を閉めると言ったときに、後継者となる決心をしたそうです。小出さんのうちはお父様の影響で他の家庭よりも「おやき」が食卓に並ぶ頻度が多く、18歳で家を出るまでは「おやき」が大嫌いだったとのこと。北信の方はみんな「おやき」が大好きだと思っていた方も多かったのか、その言葉を聞いてびっくりしていた聴講者の方もいらっしゃいました。
「おやき」の原型が富士見町に?

講演会の様子2
小出さんがおやき屋を継ぐまでの話を聞いた後は、パワーポイントから出題されるクイズに答えながら「おやき」の歴史を教えていただきました。
諏訪地域はあまりなじみがないように思っていましたが、「おやき」の原型と思われるものが縄文時代にはすでにあり、意外にも富士見町の遺跡から発見されたとのことです。
また、おやき文化が根づいている地域では年間を通して「おやき」を食べる風習があり、これもまた私たちにとってはびっくりなことでした。
郷土食は「家庭の一品」から始まる
「おやき」の歴史から始まり、全国の「おやき」について、県内の「おやき」の種類など色々なお話を聞いて、何気なく買って食べていた「おやき」は本当に奥の深いものだということがわかった講演会でした。
小出さんの話のなかで、「自分が食べていた家庭の味(おやき)が無くなってしまう、二度と食べられなくなってしまうと思った時に、おやき屋を継ごうと決心した」という言葉を聞いてハッとしました。また、郷土食とは特別なことではなく、家庭の食卓の中にあり、我が家の味を次世代に繋いでいくことで郷土食の伝承となると話されていました。
「郷土食の伝承」というと難しく捉えてしまいますが、小出さんが話していたようにそれぞれの家庭の味や一品を親から子へ、子から孫へと伝わっていくことだと思えば母や祖母が作ってくれていた料理を教わってみようかな。自分の子どもと一緒に作ってみようかな。という気持ちになるような気がします。
今回の講演会で、「おやきの作り方が知りたかった」「実演が見たかった」「おやき講座をやってください」という声を多くいただきました。後日談ですが、講師の小出先生にも伝えたところ、「是非!」とのお返事をいただきましたので、次年度どこかで企画できたらいいなぁと思いますので、よろしくお願いいたします。多くの市民のみなさまに参加していただいたことで、「郷土食」や「おやき」にとても興味があることがわかりました。ありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1177)





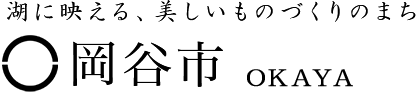
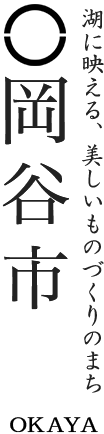





更新日:2024年11月19日